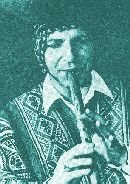ケーナについて
------------------------------
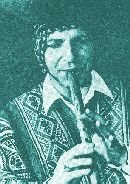
●ケーナの歴史:ケーナの歴史は古く紀元前にさかのぼると言われています。遺跡からも骨や土で作られたケーナが出土しています。その後、西洋音階の影響を受けて現在のような形になりました。材質は、以前はカーニャという葦で作られたものが主流でしたが、現在は竹を使ったものや、木をくりぬいたもの、牛骨や黒檀で作られたケーナもあります。日本でケーナが広まったのは1970年代にサイモン&ガーファンクルが演奏した「コンドルは飛んで行く」がヒットしたおかげです。それと前後してアルゼンチンやボリビアの音楽が日本に紹介されて知られるようになりました。
●ケーナの種類:G管といわれるケーナがもっともポピュラーなものです。これは基音がソの音です。これより1音低いF管、ケナーチョといわれる基音がレのD管などあり、曲によって吹きわけることがあります。
●ケーナの吹き方:ケーナの構造はリコーダーなどと違いリードと呼ばれるものはなく、尺八と同じ原理で歌口に息を当てて音をだします。そのため、きれいな音がでるようになるまでに時間がかかります。
(1)唇をキュッと閉じて、中央にわずかな息の通り道をつくります。頬の筋肉を使って唇を左右に引っ張ります。
(2)歌口の内側が下唇に引っ掛かるような感じでケーナを下唇にあてます。
(3)できるだけ細くとがらせる感じで歌口に息を吹きつけます。ケーナをあてる位置や角度が合わないと音がでませんので、いろいろ試行錯誤してみてください。
■■■ MENUへ!
このページのTOPへ! ■■■
**************************************************
【番外編】
ケーナ ある ある ある
同好会の活動からの
ケーナ(フォルクローレ)練習や演奏あるある集
なので
それぞれの詳しく(正しい情報)は他のHPを参照下さい。
■ケーナを始める 編
ケーナは、筒を咥えたら絶対に「音」は出ない!
・ケーナは、“ちくわ”のような筒状です。
・上部にU字・V字に削った『歌口』があります。
ケーナの原理は、尺八・フルートと同じ!
・息を『歌口』の溝に狙って当てて音を出します。
・息を内側と外側に分かれるように吹入れます。
・「伝助さん(古~ぃ!)」のように首を振らなくてよい。
ケーナは、音を出すのが難しそうに見えて、実は簡単!
・唇と歌口の ”音の出る位置” を見つける・・・だけ。
・音さえ出てしまえば、指使いはリコーダーと同じ。
・ケーナ造りのイベント会場で 初めて触れて
初めて音が出る人が多いです。(特にお子さん)
・一見は”難しそう”に見える楽器なので、
音が出るところを見つければ、誰でも即 HERO!
※ケーナは木管楽器の”エアリード(楽器)”種になります
仲間には
フルート・ピッコロ・尺八・篠笛・リコーダ
・オカリナ・ティンホイッスル他 が、あります。

左が “でっケーナ” 「D管」正しくは「ケナーチョ」
真中が “通常ケーナ” 「G管」 ・
右が “ちっケーナ” 「A管」演奏のために作成頂いた
このページのTOPへ! ■■■
■ケーナが欲しい 編
演奏するなら楽器店、演奏者 等からの購入が無難!
・日本ではほぼ楽器として使用できるものが
売られています。
・飾ることを主体としていて、奏でるのには
不向きなケーナもあります。
ケーナに “音程の微調整”を行う“仕組み” はない!
・素材は基本的に、葦(カーニャ)・竹(バンブー)等
”自然素材”です。
・”自然素材”で作成したケーナには、まったく同じ
製品はありません。
音色も音程もみんなと同じにする近道は、
同じ製作者の同じ素材のケーナで揃える。!
・ケーナに音程調整の装置はありません。
・演奏技術で合わせることも出来ますが、
技術(テクニック)が必要です。
・ピッチが合ってないアンサンブルは、
民族音楽らしくポク・・・”味”になる。。カナ
指使いがあっていればその音程が出るとは限らない!
・合唱の時、みんなと同じ抑え方をしているのに
知違う(ずれた)”音程”が出ることがある。
・チューナーを購入して音程を確認しながら
練習することをお勧めします。
演奏仲間があちこちにできると
ケーナの所持本数も増える!
・奇麗なハーモニーにするため、
音程(orピッチ)の合ったケーナを揃えたくなる。
・音色を合わせるため、
同じ材質のケーナを揃えたくなる。
∴ したがって どんどん増える
音色は、主に太さや材質で異なります!
・・・ と思っていたら
海外のプロの方に私の“ケーナ”を貸したら
その方の音色(ほぼCDと同じ)で演奏していた。
(-_-;
※民族音楽(伝統音楽)楽器には、
”ピッチ”という考えはなかった・・・ようです。
・西洋音楽で言う所の
アンサンブルを楽しむようになってからのもの?

尺八、篠笛、手作りリコーダが紛れ込んでる
わかるかなぁ〜 わかんねぇだろうなぁ〜
このページのTOPへ! ■■■
■グループ演奏 編
とりあえず『コンドルは飛んでいく』を
演奏しておけば・・・!
・ピアノなら「エリーゼのために」
ギターなら「禁じられた遊び」
ケーナなら「コンドルは飛んで行く」
・ ”人集め” や ”飽きてそうな観客” に向けて
最強な選曲。
・仲間内での演奏会や打上での演奏には”度胸”が必要。
・ダントツ人気の曲だけど、大正時代に出来た古い曲。
・有名にしてくれたサイモン&ガーファンクルの
歌詞には ”コンドル” が出てこない。
演奏者が、演奏中に顔を見合わせている時は・・・!
<曲を間違える>
・曲(メロディー)を間違って演奏し始める人ほど、
堂々と演奏している。
・・・が、気付いた時にフェイドアウト
・”弦”部隊がイントロを間違えることも。。。
<出だしを間違える>
・ “フライング・ミス(飛び出し演奏)” は、
本人だけが気付かない。
・他のメンバーが
フライングした人に合わせて継続。
<迷子になる>
・繰返しの多い曲は、今が何回目の繰り返しか
分からなくなりやすい。(他のメンバー頼り)
<怖い目線>
・演奏中、今のミスは俺ではないのに、
みんなが ”まず” 俺を見る・・・ (-_-;
『楽器の説明』は時間稼ぎか、お客様を起こすため?
・MCで演奏曲数を減らし、その間メンバーは休憩。
・長めのケーナは「でっケーナ」、
短めのケーナは「ちっケーナ」・・・で、受け狙い。
・客席から「オカリナじゃないんだ・・・」の声が。
外でケーナを紛失したとき・・・
・忘れ物の係に「ケーナ」を説明しても
「リコーダ」・「尺八」・「オカリナ」が出てくる。
手拍子やリズムをとってくれてると うれしいぃ〜!
・演奏者はおだてに乗りやすい。
・客席にスペイン語がわかりそうな人を見つけると
・・・唄声が小さくなる。
演奏中の駆け声は潤滑油!
・民謡の「ハイハイ!」「どうしたどうした!」
フラメンコの「オ〜レッ!」・・・と、類似した
”合いの手” を客席から頂くと、演奏者は元気になる。
・だが、演奏者側での掛け声が調子に乗り過ぎると、
お客様は引いていく。
・・・サッカーの「ゴォ〜ォ〜ォ〜ル!!!」の
アナウンスでこちらが冷めるのと同じ。
※お客様は演奏中でも
「手拍子」・「足拍子」・「又拍子」・「掛け声」
・「立って踊り」・「お子さんの鳴き声」等、
自由にお楽しみください。

アルマジロを利用した“チャランゴ”
ケーナと“サンポーニャ” ・
後ろに“ボンボ”も写ってます ・
このページのTOPへ! ■■■
■サンポーニャ 編
サンポーニャとは
・”カーニャ”という葦を節で切り
長さの異なる管を音階順に並べた楽器です。
・”パンパイプ”と呼ばれる楽器種です。
・最近は”カーニャ”が不足しており
”竹” や ”プラスティック”制 に なってます。
ビール瓶を吹き鳴らすのと同じ構造です。
・最近は瓶との出会いが少ないので伝わりにくい。
練習当初は音が小さいので近所迷惑になりにくい。
・大音量を出そうとムキになると、
頭がクラクラ(倒れそう)するので、要注意です。
・安く早く酔いたい時は、
飲みながらのサンポーニャ演奏が有効です。
・・・良い大人はマネしないこと!
「コンテスタード」が基本の演奏法です。
・ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ・ラ 音の管 担当者と、
レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ 音の管 担当者が
二人で一つのメロディーにして演奏する。
・・・”コスパ”の悪い演奏法。
・祭りなど、大勢の人たちが
二つの列管のサンポーニャに分かれて
歩きながら一つのメロディーを演奏する方法が主流。
(シクリアーダと呼ぶ)
・・・歩きながらだから”サンポ(散歩)にゃ。
・演奏中に間が開いてしまうと
「お前の番じゃないのか!」と
お互いを ”責めた目” で睨み合う。
ケーナと同じで音程の調整装置はない。
・豆や米などを管に入れて音程を上げることで調整。
・購入後に音程を下げることはできない。
演奏本番中に起こりやすいアクシデント・・・
・各管を結んでいる紐が緩んで全体がバラバラになる。
・音程調整のために管に入れた豆を舞台にバラまく。
・使う管が ”列” から徐々に沈み、ズレいく。
葦等、素材が大変”弱い”ので・・・
・つぶれ、ひび割れしやすいので保管は要注意!
・貸し出しの時はハラハラして目が離せない。
・管の”割れ”に気付くのは大抵が本番直前
・・・瞬間接着剤は必需品!
演奏で唇下を傷つけてしまうことがある。
・明日の演奏に備えての練習時によく起こる。
・塩化ビニール等の“透明素材”のサンポーニャでの
演奏時の怪我(出血)は ・・・悲惨なビジュアル。

赤い帯の 「マルタ」(標準) ・
緑帯の 「サンカ」(低め) ・
他に小さい「チュリ」(高い) ・
身長ほどの「トヨ」 (とても低い)がある
このページのTOPへ! ■■■
■弦楽器 編
スペイン人が持ち寄ったギターから
「チャランゴ」が生まれた
・アンデスには「弦」の文化がなかったので
「弓」系の武器なく
スペインに敗れたとの説もあるとかないとか。
知らんけど・・・
・マンドリンに似て胴体は丸いものが多く、
素材は、木をくりぬいた木製ですが
”アルマジロ”の甲羅を利用したものもあります。
・楽器説明で
「チャラぁ〜んと鳴るからチャランゴ」・・・は定番
「アルマジロ製は毛が伸びます」・・・も定番。
・弦楽器の弦が切れるのは、大抵が本番中。
・5コース10弦なので、本番中に弦が1本切れても
何とか演奏は続けられる。
・弦を “張り替えた”のが何時なのか ・・・覚えていない。
・複弦なので、音程調整(チューニング)時に
目的と違う弦を間違って引っ張り続けると・・・悲惨!
・紛失時、忘れ物の係員に「チャランゴ」を説明しても
「ウクレレ」が出てくる。
楽器説明「ギター」は説明時間が短いか省略されがち。
・ギター担当者は、
ここで笑いが取れるかが実力の見せ場。

チャランゴとマンドリン
複弦の組み合わせは違うが共に10弦
このページのTOPへ! ■■■
■打楽器 編
太鼓の名称は「ボンボ」
・楽器説明で
「太鼓は”ボンボン”と鳴るからボンボ」・・・は定番。
・“なめして”なく毛がそのままなので、
お客様に触れて頂いて時間を稼ぐ。
・叩いて毛が抜けた部分を「アルシンド」と言っても
古くて通じない。
・湿気に左右されやすく、音色が変わりやすい。
カスタネット代わり?の「チャフチャス」
・楽器説明で
「チャフチャスは何で出来ていると思いますか?」
正解は・・・ 我々のLIVEにいらして確認して下さい。
・紐が切れて舞台中にバラケ散ることが起こるのは
大抵が本番中。
このページのTOPへ! ■■■
**************************************************
■フォルクローレで演奏される主な国々と楽曲
南アメリカ(アンデス)
・アルゼンチン・・・ 「花祭り」等
・ボリビア ・・・ 「泣きながら(ランバダ)」等
・チリ ・・・ クエッカ、トナーダ
・コロンビア ・・・ クンビア
・エクアドル ・・・ サンファニート
・パラグアイ ・・・ 「鐘つき鳥」等
・ペルー ・・・ 「コンドルは飛んで行く」等
・ベネゼーラ ・・・ 「コーヒールンバ」等
他
**************************************************
■■■ MENUへ!
このページのTOPへ! ■■■
|